はじめに
不妊治療を検討する際、最も気になるのが費用です。特に人工授精や体外受精は高額になることが多く、治療の継続を悩む方もいるでしょう。本記事では、それぞれの治療の費用について詳しく解説し、助成制度の活用方法についても紹介します。動画もありますのでこちらもどうぞ。
人工授精の費用
人工授精は負担の少ない不妊治療であり、費用も抑えられる傾向があります。僕たちの産院でのかかった大まかな費用です。
- 一般不妊管理料:750円
- 診察・検査・薬代:約9500円
- 人工授精1回:5460円
- 1周期での合計費用:約15,710円
病院によって費用は異なるため、事前に確認することが重要です。また、人工授精の成功率を考慮し、治療回数をどの程度にするかも検討すべきポイントです。僕たちの通っていた産院では3,4回で妊娠しなければ、体外受精に進むという考えの産院でした。
体外受精の費用
体外受精は高度な技術を必要とし、費用も高額になります。ただ、保険適用になっているので、高額療養費制度が使えるのである程度は抑えられることになります。一般的な治療費の目安は以下の通りです。
採卵
- 生殖補助医療管理料:900円
- 診察・検査・薬代:約35,000円
- 採卵10個:約31,200円
- 受精:約12,600円
- 培養(胚盤胞5個まで):37,500円
- 胚凍結5個:21,000円
合計:138,200円
採卵は一回で卵子が複数取れれば、再度行う必要がないが負担としては大きくなる。
移植
- 生殖補助医療管理料:900円
- 診察・検査・薬代:約15,000円
- アシステッドハッチング:3,000円
- 凍結融解移植:約36,000円
合計:54:900円
胚移植の保険適用は一子につき6回までであるため、それを超える場合は自己負担となってしまいます。そうなってくると1回あたりの移植も20万円程度かかってくるため、負担もさらに大きくなる。現状、自己負担に対する助成金も保険適用に伴いなくなっているため産院の軽減措置等に頼るしかない。
費用を抑えるためのポイント
治療費を抑える方法として、以下のポイントが挙げられます。
- 産院選び:治療費が施設ごとに異なるため、口コミや評判を調べて慎重に選ぶ
- 高額療養費制度:保険適用の場合は、年収に応じて高額療養費制度を活用しよう
産院によって治療費や方針も異なるため、自分たちに合った産院を選び後悔しない選択をすることが大切です。高額療養費制度を活用することでひと月の同じ病院での医療費が一定額を超えた場合、超えた額が免除になるため、負担も減ってきます。今はマイナンバーカードと保険証を連携することで自動で高額療養費を計算してくれるため便利です。ただ、2025年の法改正から高額療養費制度の負担額が段階的に増加する方向に話が進んでいるため、負担としては増えていってしまうことが現状です。高額療養費の年収と上限額は全国健康保険協会のサイトをご確認ください。
全国健康保険協会サイト:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
まとめ
不妊治療は金銭的な負担だけでなく、精神的な負担も大きいものです。パートナーや家族と十分に話し合い、費用や治療方針について納得した上で進めることが大切です。助成制度をうまく活用しながら、自分に合った治療を選択することで、経済的な負担を軽減しつつ前向きに進めていけるでしょう。本記事が、不妊治療の費用を検討する際の参考になれば幸いです。




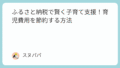

コメント