はじめに:「なんとなく」では乗り切れない育児とお金の話
「育児っていくらかかるの?」という疑問は、多くのプレパパ・プレママが一度は抱くもの。
でも実際は、年齢やライフステージによって“かかる金額”も“貯められるタイミング”も大きく変化します。
必要なのは、感覚ではなくライフステージごとの「かかり時」と「貯め時」を知ること。
この記事では、出産から高校卒業までを6つのステージに分けて、支出と貯蓄のタイミングを整理していきます。
ステージ1:出産前〜1歳|「出費は多め、でも固定費削減で貯めやすい時期」
かかり時
- 出産準備品(ベビーベッド、抱っこ紐、チャイルドシートなど):5万〜15万円
- 出産費用(保険適用外部分含む):5万〜10万円(ただし一時金の支給あり)
意外とかさむのが出産・育児グッズ関連。新品にこだわると10万円を超えることも。ただし親や知人からの“お下がり”やメルカリなどを上手に使えばかなり抑えられます。出産準備費必要なのもはこちらも確認。
貯め時
- 育休中に「通勤・外食・交際費」が減る
- 子どもの生活費が比較的かからない
この時期は、意外にもライフスタイルの変化により“自然と支出が減る”ため、しっかり見直せば貯蓄に回せる月も。コロナでお家時間が増えた時も家系的には出費が減ったのではないでしょうか!?赤ちゃんのための消耗品は必要になりますが、無駄な出費はが減れば貯蓄も可能に。
ステージ2:1歳〜保育園年長(0〜5歳)|「保育料と習い事が支出の中心」
かかり時
- 保育料:所得によるが月2〜4万円程度(公立・認可園の場合)
- 習い事(英語・水泳など):月5,000円〜1万円/1科目
- おむつやミルク代(1〜3歳ごろまで):月5,000〜8,000円
特に共働き家庭にとっては保育料が固定費として重くなる時期です。
また、まわりの子が習い事を始めだすため「うちもそろそろ?」と焦りがちに。0歳~5歳までにかかる費用をまとめていますので、参考にして5歳までにかかる費用をざっくり算出することで、出費を恐れず過ごせます。
貯め時
- 児童手当(月15,000円〜)をそのまま貯金
- 保育園給食による食費軽減
- 習い事を「厳選」することでコスト最適化
子ども本人の希望より“親の期待”が先行しがちな時期。教育費をかけすぎず貯蓄に回せるかがポイントです。この時期に運動神経が育つ時期ではあるので、いろいろな経験をさせるのはいいが、習い事か地域のイベントを活用するかはそれぞれの家庭次第。
ステージ3:小学校低学年(6〜8歳)|「手が離れはじめるが、意外と見えにくい支出も」
かかり時
- 給食費:月4,000〜5,000円
- 学用品や学校行事費(遠足、体操服など)
- 習い事:1万〜2万円/月(掛け持ちが増える)
義務教育だからと油断しがちですが、実際には学校関連費+習い事で月2〜3万円かかることも。子供のやりたいことを優先させてあげるのが一番ではあるので、何に興味があるのかをしっかり見ていてあげることで、さらに伸ばしてあげる手伝いができるかも。
貯め時
- 学童利用を減らすことで一部固定費削減
- お小遣いや物欲がまだ少ない(本人の要求が控えめ)
この時期は「学童卒業+習い事セーブ」で支出に余裕が出やすい時期です。貯められる家庭はここで積立を強化すると◎。子育ての中で一番の貯め時である時期になるので、これからの支出に備えて大学のために15年の長期で投資を考えるのもよいと思います。
ステージ4:小学校高学年(9〜12歳)|「塾と進学意識が“かかり時”を加速」
かかり時
- 学習塾代(集団指導):月1.5〜3万円+季節講習
- タブレット学習や通信教材:月3,000〜6,000円
- 習い事+クラブ活動:2万円前後/月
中学受験の有無に関係なく“勉強への投資”が増える傾向にあります。地方ではそこまで中学受験は多くないですが、都心では中学受験が当たり前。住んでる地域によって考え方も変わってくるため、周りに合わせるべきか家族でよく相談するのが良いと思います。小学校時代にかかる習い事の費用についてもまとめていますので、参考にしてみてください。
貯め時
- 習い事を「続けるかやめるか」でメリハリが生まれる
- お金の使い方を子どもと一緒に学び始める時期に
支出が増えてきますが、逆に「何をやめるか」を見直すチャンスでもあります。子供の興味が変わってくるころでもあります。自分の将来の夢を何かに書いたりすることが増えて、何をしたいのかが明確化してくる子もいます。将来の夢がまだあまり決まっていないという子でも、これまでと違った経験をさせることでやりたいことが決まることもあるので、今やっていることを「やめる」という選択も一つに考えるとよいでしょう。
ステージ5:中学生(13〜15歳)|「支出の加速フェーズ、貯め時は限定的」
かかり時
- 塾(月2〜4万円)+教材費・模試・受験対策講習
- 制服代・部活動費・修学旅行・定期券など
- スマホやデバイス代+通信費
中学では“子ども1人分のコストが大人並み”になることを実感する家庭が多いです。部活動が本格的に始まることで、運動部だと食事の量も大人と同じに。生活費も完全に一人の大人と変わらないので、ここからはどうしても出費が増えてきます。
貯め時
- 家計の固定費を見直す(保険・住宅費など)
- 児童手当の終了後を見越した貯蓄計画の再編成
基本的には「耐える時期」ですが、見直しできる項目があれば積極的に対応したいところ。電気代や1年更新の保険、サブスクによる固定費の見直しをしてみてもいいかも。電気代は、電力会社の乗り換えで費用が安くなることもありますし、必要な火災保険や自動車保険も価格比較によって同じ保証でさらに費用を抑えることもできます。見積もりは基本無料なので、見積もりすることで現状の費用が抑えられているのかの確認にもなります。
ステージ6:高校〜大学入学前|「出費ラッシュ到来に備える終盤戦」
かかり時
- 高校の授業料(公立は無償だが私立・制服代は高額)
- 予備校や塾、模試代:月2〜5万円
- 大学進学に向けた積立・受験費用:数十万円規模
このステージは「教育費のピーク」を迎える重要な時期。
大学進学を控えた家庭では、年間100万円以上の支出も珍しくありません。国公立の大学か私立の大学に進学するかで、大学の学費が年間55万~100万越えと倍近く変わってくるため、大学まで見据えた計画を立てておくのが重要である。
貯め時
- 高校無償化により授業料がかからない分を積立
- 子どももアルバイトなどで家計意識を学ぶタイミング
子どもの自立も徐々に始まるため、家計を「家族全体で支え合う」方向へ。アルバイト禁止の学校もあるので、一概には言えないが社会を学ぶ上でアルバイトの経験はよい経験だと思う。大学の進学も真剣に考えてくれるかも。一方で、自由に使えるお金を手にしてしまうことで、あらぬ方向へ育ってしまうこともあるので気を付けなければ…。
まとめ:計画と“緩急のバランス”が家計を支える
育児には「毎月コンスタントにかかる費用」と「あるタイミングでドンとかかる費用」の2種類があります。
重要なのは、“かかり時”に焦るのではなく、“貯め時”を見極めて備えておくこと。
そして、過剰な節約ではなく「家族にとって必要な支出はかける」柔軟さを持つこと。
我が家も完璧ではありませんが、こうしたリズムを意識することで、これからに備えて貯蓄や投資を活用して、未来に備えています。

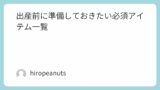




コメント